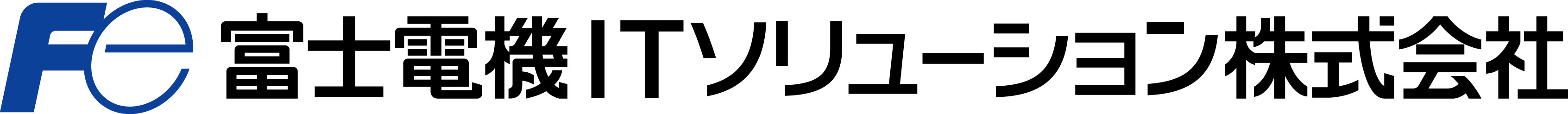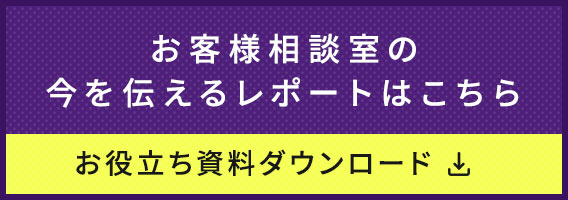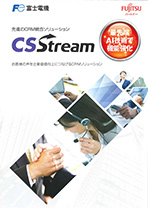VOCのビジネス活用を効果的に進めるためのCRM選び

“2025年の崖”克服に向けたDXの取り組みの一環で、データ活用を進める企業においては、いかに効率よく必要なデータを用意するかが課題となる。こうした企業が注目するのがVOC(Voice Of Customer)だ。しかし、営業やマーケティング、品質管理などの様々な部門が、取引先や製品・サービスのエンドユーザから寄せられるVOCをバラバラに管理・活用していて、全社で有効活用できていないケースが多い。また、エクセルなどを使ってVOCを管理しているケースも多く、属人化が進み、全社での一元管理を妨げる大きな要因となる。VOCを活用のメリットや収集の課題などに触れつつ、ビジネス活用を効果的に進めるアプローチについて考察する。
DX推進に向けてVOCに再び脚光が
文字どおり「顧客の声」を意味するVOC。コールセンターなどで蓄積される膨大なVOCについては、かなり昔から“宝の山”と言われてきたが、かつては電話の音声をテキストデータ化する負担が大きく、なかなか活用が進まなかった。また、会話内容をエクセルなどに入力して管理する方法では、人によってまとめ方が異なり、活用に適したデータになっていないケースも多かった。
しかし、インターネット時代に入り、取引先やエンドユーザとのコミュニケーションも大きく様変わりした。かつては、電話やFAX、郵便しかなかったのが、そのままデータを活用できるメールやチャットなどの手段が普及。さらに直近では、音声認識や生成AIなどの急速な進化により、音声(会話内容)を高精度でテキスト化したり、要点を押さえたサマリを自動で作成したりといったことが可能になった。このようにVOCの電子化・データ化が容易になると同時に、ここ数年のDXブームでデータ活用の重要性が叫ばれるようになり、改めてVOC活用に取り組む企業が増えたというわけだ。
コールセンター以外にも下記に挙げるように、部門レベルでそれぞれ目的をもってVOC活用を進める企業は多い。しかしながら、多くはVOC活用が部門の中で閉じていて、DXにつながるような全社的な取り組みになっていないケースが一般的だ。
- マーケティング部門:実施したマーケティング施策に関する評価・評判を探り、次の施策立案のヒントを抽出する
- 商品開発部門:市場ニーズやトレンドを探り、新商品開発の参考にする
- 品質保証部門:主としてクレーム情報を元に、提供する製品・サービスを改善・改良する
- 広報部門:継続的にSNSのクチコミ情報を抽出し分析することで、ブランドイメージの測定、維持・向上を目指す
- 営業部門:顧客を対象にアンケートを実施し、満足度を測定、離脱を防ぎロイヤルティ強化につなげる
VOCの収集方法と課題(留意すべきポイント)
VOCを収集する方法は下記に挙げるとおり様々あるが、傾向としては顧客の利便性や負担を考慮した手法にシフトしつつある。
コールセンターを活用
コールセンターでの問い合わせ対応・VOC収集方法で大半を占めるのが電話であり、重要な役割だ。また、一部FAXも併用して対応をしているコールセンターもあるが、いずれの場合もVOC活用に向けてテキストデータ化が必要で、コールセンター部門の負担が大きい。
問い合わせ用のメールやチャット、Webフォームを導入
電話に代わり現在主流となっているのが、メールやチャット、Webフォームによる問い合わせだ。コールセンター人材が不要、24時間問い合わせ可能など、企業・顧客の双方にとってメリットが大きく、デジタルでやりとりをするためのデータ化の必要がなく、VOC活用に適した収集方法と言える。
アンケートやインタビューなどの調査を実施
アンケートやインタビューを実施して顧客に直接聞くという方法もある。アンケート調査に関しても、紙で回収する方法に代わり、PCやスマホで回答できるインターネット調査が普及。データ化の手間なしに分析・活用できるようになった。
SNSなどクチコミ情報を活用
消費行動に大きな影響を与える情報として無視できないのが、SNSやECモールのコメント欄などに溢れるクチコミ情報だ。公開されている情報だけに細かなプロフィール分析はできないが、ブランドイメージの向上を目指す上で、自社や競合会社の製品・サービスに関するクチコミ情報の分析・活用は有効だ。
様々な方法で収集可能なVOCだが、全社規模の活用により変革をもたらすには、収集段階においていくつか留意すべきポイントがある。
必要な基礎情報を確実に押さえる
問い合わせ内容をエクセルに入力して管理している企業は多いが、属人化により情報の粒度や正確性にバラツキがでてしまいがちだ。記録を見てもクレームなのか、単純な問い合わせなのか、わからなければカウント不能になってしまう。分析のしやすさを考えるならば、コールセンターでは単に聞いた内容をメモするだけでなく、押さえるべきポイント(基礎情報)を予め決めて、聞き漏らすことがないようにしたい。
部門で閉じることなく全社一元化を目指す
製品に関するクレーム情報ひとつとっても、エンドユーザからコールセンターに電話が入るケースもあれば、販売店を経由して営業部門に連絡が入るケースもあり、別々に管理していては全体の傾向分析は難しい。また、コールセンターに集まる問い合わせ情報と、広報部門が収集したSNSの情報を組み合わせて分析することで、単に傾向を分析するだけではなく、新たな仮説を導く可能性もでてくる。各部門がそれぞれのやり方で収集したVOCを1ヵ所に集めて、統合的に分析できる基盤の構築が望ましい。
VOC活用とCRMの必要性
収集したVOCを一元管理し、全社活用を進めるとなると、そのためのツールの導入が欠かせない。コールセンターに寄せられる膨大なVOCを登録した上で、Webフォームやメールによる問い合わせ情報を統合する形で、全社で閲覧・分析できるVOC統合基盤を構築するなら、CRMツールの導入がお勧めだ。顧客属性などの押さえるべきポイント(基礎情報)を項目立てすることで、属人化することなく、分析に適した基礎情報を効率よく整備することができる。
昨今話題のAI機能を搭載するCTIと連携すれば、コールセンターでの会話のテキスト化や要約作成をした上で、CRMに自動登録が可能だ。コールセンター以外の部門のメンバーも、VOC分析を進めるなかで必要に応じて全文検索・キーワード検索するなどして、特定の会話について直接内容を確認できるようになる。
VOCのビジネス活用を支援するコールセンターCRM「CSStream」
あらゆるVOCを一元管理して全社で活用する“理想”を追求する上で有効なCRM導入だが、その際、いくつか留意すべきポイントがある。
まず、情報セキュリティの観点から、きめ細かなアクセス制御に対応する必要がある。VOCの属性情報には個人情報も含まれるため、部門によってどこまで参照できるかを細かく設定できる製品を選びたい。また、意外に見落としがちなのが全社で活用する際のコストだ。ユーザライセンスの製品の場合、全社で利用するとコストが膨大になってしまうため、どうしても特定部門に絞って導入……となりがちだ。このほか、興味関心に応じて部門ごとに異なるダッシュボードを表示し、必要な情報にすぐにたどり着ける機能なども重要だ。
こうしたVOC全社活用の観点でお勧めなのが、富士電機ITソリューション株式会社が提供するコールセンターCRM「CSStream」だ。部署・個人単位で、きめ細かく参照権限(お客様情報の公開レベルなど)を設定でき、ダッシュボードも現場レベルで容易に作成ができる。サーバライセンスを基本(150ユーザライセンス付)とし、閲覧するだけのユーザはライセンス料不要のため、コストを気にせず社内で利用を拡大できる。
パッケージ製品でありながら、業界・業種や個社ニーズにあわせたカスタマイズにも柔軟に対応。リリースから20年以上、幅広い業界・業種のユーザ数は10万人以上を誇る「CSStream」。貴社の現状や目的にあわせたVOC活用を、アカウントSEが伴走型で支援するので、まずは気軽にお問い合わせいただきたい。